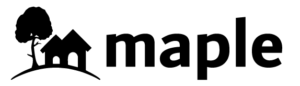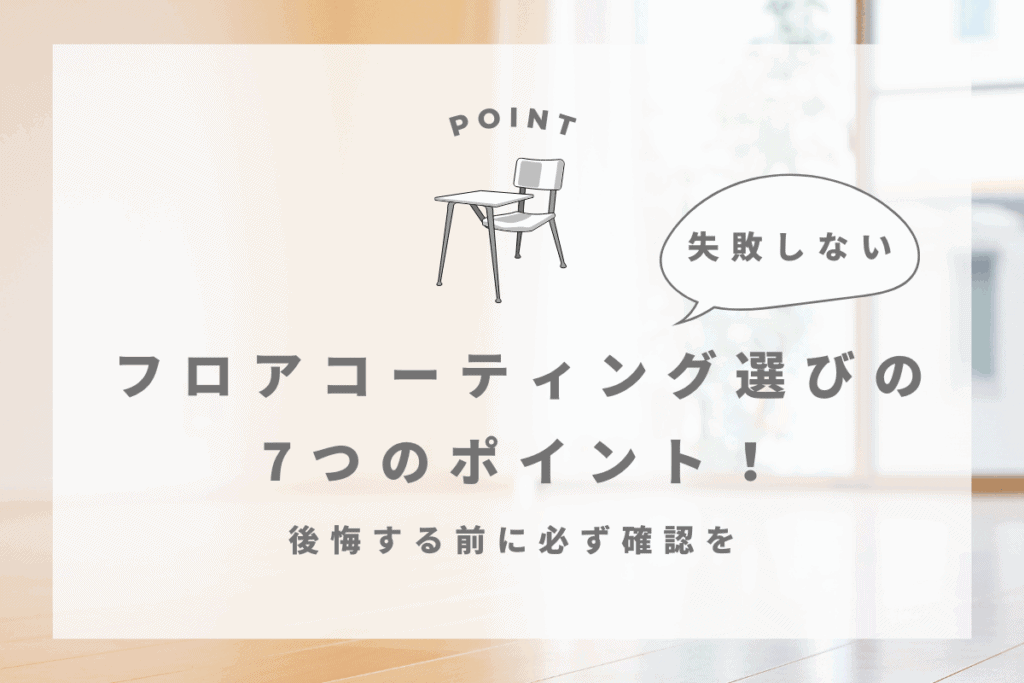フロアコーティングは、住まいやオフィスの床を美しく保ちつつ、傷や汚れから守るための施工方法です。しかし、種類や業者が多く「何を基準に選べばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、フロアコーティングで後悔しないために押さえておくべき7つのポイントを、わかりやすく解説します。はじめて検討する方でも安心して読める内容なので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。
1. コーティングの種類を理解する
フロアコーティングには主に以下の3種類があります。
- シリコンコーティング(メイプル社ではグリップワンという商品名)
滑りにくく、防汚性に優れており、ペットや小さなお子さん、高齢者のいる家庭に人気です。ただし、耐久性はやや劣ります。 - ガラスコーティング(メイプル社ではプライムコートという商品名)
高い硬度と耐摩耗性を誇り、見た目も美しく高級感があります。10年〜20年ほどの長寿命で、メンテナンスの手間を減らしたい方に向いています。 - UVコーティング(メイプル社ではUVコートという商品名)
紫外線で瞬時に硬化させるため、当日中に使用可能になるのが特徴。工期短縮が必要な現場や商業施設で採用されることが多いです。
床材やライフスタイルに合ったコーティング剤を選ぶことが、暮らしの満足度に直結します。
2. フロアコーティングの本当のメリットを知る
見た目の美しさを長く保つだけでなく、実用性にも多くの利点があります。
・床に傷や汚れがつきにくくなる
・掃除がしやすく、衛生的
・滑り止め効果で安全性がアップ
・経年劣化による色褪せを軽減
・フローリングのツヤ落ちを軽減
・ペットの引っかき傷を防ぐ
つまり、見た目だけではなく「快適性」と「安全性」も大きく向上するのがフロアコーティングの魅力なのです。
3. 価格の相場と内訳を把握する
費用は、施工面積・コーティングの種類・業者によって異なりますが、相場としては1㎡あたり3,000円〜8,000円程度です。
たとえば、70㎡の住宅でガラスコーティングを行うと、30万円〜50万円が目安になります。これに加えて、以下のような追加費用が発生することがあります。
・下地処理費用(洗浄・研磨など)
・養生費用
・家具の移動費用
・施工後のメンテナンスオプション
あまりに安すぎる価格を提示する業者は、手抜き工事や耐久性に不安がある場合もあるため要注意です。
4. フロアコーティングは本当に必要?
「そもそも必要なのか?」と迷う方もいるかもしれませんが、フロアコーティングは長期的な視点で見ると非常にメリットが大きい施策です。特に以下のようなケースでは施工を検討する価値があります。
・新築またはリフォーム直後の状態を長く維持したい
・小さな子どもや高齢者、ペットがいる
・掃除の手間を減らしたい
・フローリングの光沢を保ちたい
最初の施工費はかかりますが、定期的なワックスがけなどの手間が減るため、結果的にコストパフォーマンスが高くなります。
5. 業者選びのチェックポイント
コーティングの品質は、施工する業者の技術力によって大きく変わります。信頼できる業者を見極めるために、以下のポイントを確認しましょう。
・施工事例が豊富に掲載されているか
・使用する材料の説明が明確か
・保証内容や期間が明記されているか
・現地調査を丁寧に行ってくれるか
・見積もりに追加費用の可能性があるか
・口コミや評判が良いか
また、「当日中に即決を迫る」「契約を急かす」といった営業スタイルの業者には注意が必要です。
6. 施工の流れと工期を確認する
一般的な施工の流れは以下のようになります。
現地調査と打ち合わせ
家具の移動と養生
下地処理(洗浄・研磨)
コーティング剤の塗布
乾燥・硬化(UVは短期間)
最終確認・引き渡し
施工の所要日数は半日〜1日が目安です。
スケジュールに余裕がある時期に施工することで、生活への影響を最小限に抑えられます。

7. よくある失敗例と回避方法
最後に、実際にある失敗例とその防止策を紹介します。
失敗例1:「安さ」で決めたらすぐ剥がれた → 材料の品質や施工技術が低かった可能性。信頼できる業者を選ぶことが大切です。
失敗例2:床がテカテカになりすぎて不自然 → 光沢の程度は事前に確認を。サンプルを見せてもらうのが有効です。
失敗例3:施工後に滑りやすくなってしまった → 滑り止め効果のあるコーティング剤を選ぶことで防げます。
失敗例4:保証がなく、トラブル時に泣き寝入り → 保証書の有無と内容を必ず確認しましょう。
まとめ
フロアコーティングは、見た目の美しさと実用性を両立することが可能です。しかし、種類や価格、業者によって差が大きいため、正しい知識を持って選ぶことが重要です。
本記事で紹介した7つのポイントを押さえることで、後悔のないフロアコーティング選びができるはずです。施工後に「やってよかった!」と思えるよう、じっくりと比較・検討してから決断しましょう。